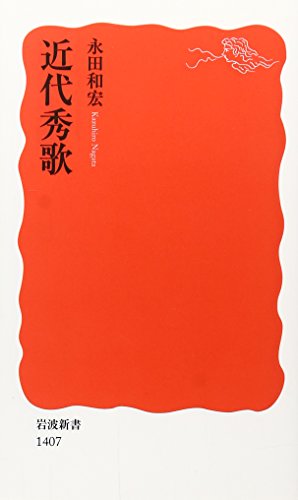映画、「ドライブ・マイ・カー」を観た。
コミュニケーションには、その場所の力というものが働く。
食卓、車、閨房…
とりわけ、この映画においては車が登場人物の台詞を引き出し、登場人物同士の会話を深めるのに大きな働きをする。
原作には、主人公の家福は車の中で、ベートーベンの弦楽四重奏をよく聴くと書かれている。僕は、映画の中でもこの曲がかかるのではないかと楽しみにしていた。それは期待通り、かかったことはかかったのだが、車の中のカセットからではなく、家福の自室のレコードプレーヤーから聞こえて来たのであった。第3番の1楽章、美しいメロディだ。
映画では、家福は車の中で音楽を聴かない。もっぱら妻の声で吹き込んだ、脚本の朗読を聴いているのだ。その習慣は妻が死んだ後も変わらない。妻とのコミュニケーションは妻の死後も続いている。
この映画には、BGMとしての音楽は一切使われない。音楽は、その場面の内部に音源が存在するときにしか聞こえてこない。外部から音楽が降ってくることはないのだ。
この映画の中では、大きくて刺激的な音が鳴ることも少ない。印象に残ったのは、車が接触事故を起こす時の衝突音と、芝居の舞台上でピストルが撃たれるときくらい。家福の車のエンジンは不快な音をたてない。
実に静かな映画だ。
そういえば、家福の死んだ妻の名前は音というのだった。